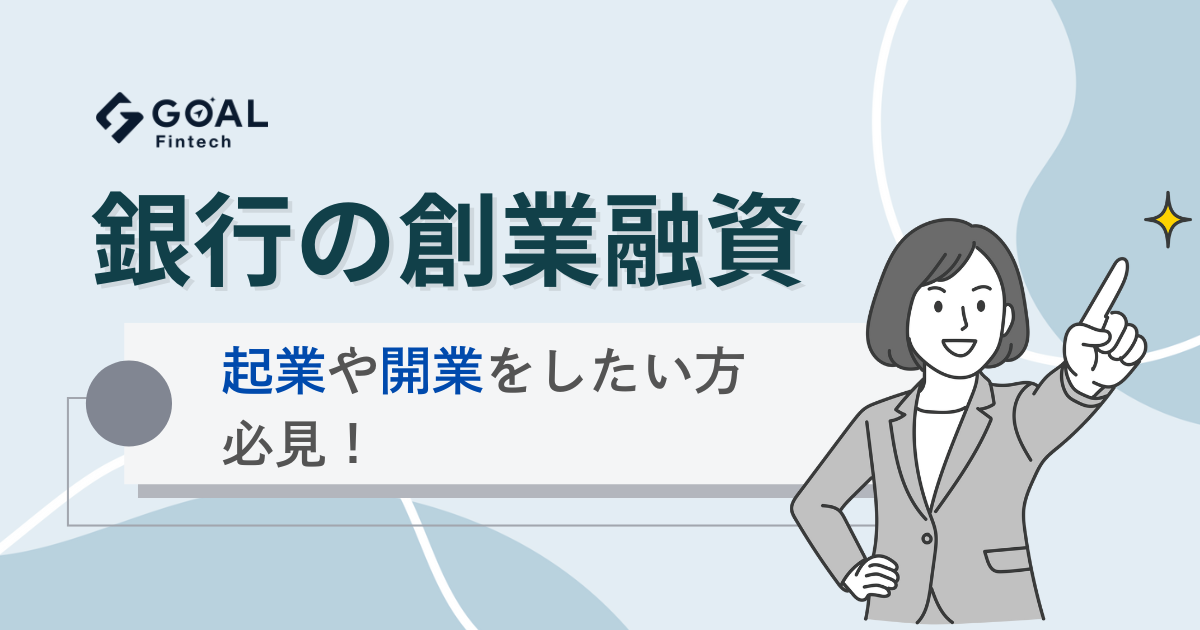起業や開業を始める際、多くの方が直面するのが資金調達の問題です。
自己資金だけでは足りない場合、銀行などの金融機関から創業融資を受ける方法があります。
創業融資は、実績のない事業者でも比較的借りやすく、低金利で資金を調達できるのが大きな特徴です。上手に活用すれば、開業後の資金繰りを安定させ、事業運営に集中しやすくなります。
特に銀行融資は金利が低い傾向にあるため、利用できるのであれば積極的に検討しましょう。
今回は、銀行融資における創業融資の仕組みやメリット、利用時の注意点についてわかりやすく解説します。
銀行で創業融資は受けられる?
新たに事業を始める場合には、仕入にかかる費用や広告宣伝費、テナントの賃料、敷金、保証金などの初期費用、営業用車両購入などのさまざまな資金が必要です。
日本政策金融公庫総合研究所の調査では、2024年の新規開業における平均費用は985万円となっており、新規で創業するには、多額の資金が必要になることが分かるでしょう。
この開業にかかる費用をすべてを自己資金で賄おうとした場合、開業資金を貯めるだけでも相当な期間が必要です。しかし、創業にかかる費用を借り入れることができれば、スピーディーに開業できる可能性が高くなります。
とはいえ、新規開業する際に、銀行で創業融資を受けることはできるのでしょうか。
結論からいうと、銀行で創業融資を受けることは可能です。
ここでは、創業融資について解説しますので、詳しく見ていきましょう。
創業融資とは?起業・開業時に使える資金調達方法
創業融資とは、起業して間もない事業者やこれから新たに事業を始めようとする方向けに設計されている融資制度のことです。
銀行などの民間の金融機関では、独立や新規創業の場合、返済能力を示す材料が乏しく、プロパー融資で対応することは難しいでしょう。
そのため、日本政策公庫の「新規開業資金」や、信用保証協会の制度融資による「創業融資」の制度を利用するケースが一般的です。
ここでは、創業融資の特徴について以下のとおり解説します。
- 設備資金や運転資金を銀行から借りられる制度
- 個人事業主・法人どちらでも利用可能
設備資金や運転資金を銀行から借りられる制度
創業融資とは、新たに開業する場合に必要となる設備資金や運転資金を銀行や信用金庫などの金融機関から借り入れるために使える制度です。
すでに事業を行なっている企業であれば、決算書などのこれまでの事業実績を示す材料がありますが、新規創業の場合には事業の実績を示す資料はありません。
返済能力があるかどうかは事業計画書などの少ない材料から判断するしかないため、プロパー融資で対応するのは難しいケースが多いでしょう。
しかし、日本政策金融公庫の提供する「新規開業資金」や、信用保証協会の「創業支援資金」などの制度融資であれば、起業・開業時でも銀行から資金を借り入れできます。
このように創業融資は起業・開業時に使える資金調達手段として有効です。
個人事業主・法人どちらでも利用可能
創業融資を受けるには、法人の設立が必要だとイメージする方も多いかもしれません。しかし、創業融資は、個人事業主・法人のどちらでも利用できます。
いきなり法人を設立して規模の大きな事業を始めるのはリスクも大きく、まずは個人事業主として開業し、徐々に事業規模を大きくしていくケースが一般的です。
例えば、美容室や飲食店で経験を積んでから独立開業する場合、個人事業主からスタートするケースがほとんどです。
特に、小規模な事業の場合、わざわざ法人を設立するメリットも少なく、個人事業主として事業を続ける方が良いケースも考えられます。
このような比較的小規模な独立開業の場合でも創業融資は利用することができます。
なお、個人事業主から法人化した場合でも、個人で創業してから7年目以内であれば、創業融資を利用できるケースもあります。
銀行創業融資の特徴
銀行で「創業融資」を受ける場合には、以下のような特徴があげられます。
- 銀行が独自に審査
- 保証協会付き融資が中心
- 公庫と組み合わせるケースも多い
それぞれ見ていきましょう。
銀行が独自に審査
銀行で創業融資を受ける場合、まずは銀行が独自に審査を行い、プロパー融資で対応できるかどうかの判断を行います。
創業融資の場合、これまでの事業実績を示す材料に乏しいケースが多いです。
そのため、代表者の経歴や提出された事業計画、資金計画などから、返済能力の有無や事業の将来性について、慎重に審査が行われます。
まず銀行が独自に審査をしたうえで、「保証協会の創業融資を利用するのか」「日本政策公庫を利用するのか」など、銀行の取組方針を決めるケースが多いでしょう。
なお、創業融資において、銀行がプロパー対応するケースとしては、担保や保証人などで保全が確保できる場合や、事業計画の実現性が高く、将来性があると判断できる場合が一般的です。
保証協会付き融資が中心
銀行の創業融資の特徴として、保証協会付き融資が中心となるケースが多いです。
先述したとおり、創業融資の場合、決算書などのこれまでの事業実績を示す材料がなく、代表者の経歴や事業計画、資金計画などの資料から融資判断をしなくてはなりません。
担保や保証人によって保全が確保できたり、実現可能性が高くて将来性に期待できるような事業計画を掲示したりしない限り、プロパー融資での対応は難しいでしょう。
こうした点から、銀行で創業融資を行う場合には、必然的に信用保証協会の創業支援制度を利用した保証付き融資で対応するケースが多いといえるでしょう。
また、信用保証協会では、新規創業者に限らず、経営に関するさまざまなサポートが行われています。保証協会の経営に関するサポートを受けたい場合、保証協会付き融資を利用していることが条件になります。
新規で事業を始める際に、経営に関するサポートが受けられるのは心強い味方といえるでしょう。こうしたサポートを受けられる点も踏まえると、創業時には保証協会付き融資を利用するのもメリットといえるでしょう。
公庫と組み合わせるケースも多い
銀行で創業融資を行う場合、日本政策金融公庫の創業融資制度と組み合わせて対応するケースも多く見られます。
創業融資は、事業の将来性を予想しにくく、返済能力の有無が不透明な場合が多いです。
そのため、銀行としては貸し倒れ発生時のリスク分散の観点から、日本政策金融公庫と協調して融資を行うケースが考えられるのです。
例えば、創業資金として1,000万円の融資を受ける場合、銀行と日本政策金融公庫の創業融資で500万円ずつ対応するといったケースが考えられます。
銀行の融資担当者としては、新規開業などの融資取組は新たな顧客開拓のきっかけにもなるため、積極的に取り組みたいと考える方が多いでしょう。
しかし、リスク面を考えるとプロパー融資だけで対応するのは難しく、公庫と組み合わせた融資対応が多くなってしまうといえます。
また、上記のように公庫と組み合わせる場合でも、銀行融資部分については保証付き融資を織り交ぜて対応するケースが多いでしょう。
なお、事業を継続させて行くには、1つの金融機関だけでなく、複数の金融機関を利用することも大切です。
例えば、1つの銀行で融資を受けたばかりでも、急な資金需要によって新たに融資が必要になるケースも十分想定されます。このような場合、同じ銀行に追加融資を相談しても審査に通らないかもしれません。
しかし、複数の金融機関を利用していると、他の金融機関で融資が受けられる可能性もあります。
事業を継続するうえでは、複数の金融機関を利用しておくメリットもあるため、公庫と組み合わせて利用するのも1つの戦略だと考えておくと良いでしょう。
創業融資で開業資金はどれくらい借りられる?自己資金との関係
銀行における創業融資について解説しましたが、創業融資ではどのくらい借り入れることができるのでしょうか。
ここでは、創業融資における借入額の目安や自己資金との関係について解説します。
銀行創業融資の借入額の目安
銀行創業融資を受ける場合、借入額の目安はどのくらいになるでしょうか。
銀行創業融資の借入額の目安について以下のとおり解説します。
- 自己資金の2〜3倍が上限の目安
- 自己資金300万円なら600万〜900万円程度
自己資金の2〜3倍が上限の目安
創業融資で借入できる金額の目安としては、自己資金額の2~3倍が上限の目安といえるでしょう。
日本政策金融公庫総合研究所による2024年の調査では、開業時の資金調達額は平均1,197万円となっており、資金調達先ごとの調達金額の内訳は下表のとおりとなっています。
| 資金調達先 | 平均調達額 | 割合 |
|---|---|---|
| 自己資金 | 293万円 | 24.5% |
| 金融機関からの借入 | 780万円 | 65.2% |
| その他 | 124万円 | 10.3% |
金融機関借入額は、自己資金額の約2.66倍となっていることから、創業融資を受ける場合、自己資金額に対し、2〜3倍程度が借り入れできる上限額と考えておくと良いでしょう。
自己資金300万円なら600万〜900万円程度
日本政策金融公庫総合研究所の調査結果を踏まえ、自己資金300万円の場合、600万円〜900万円程度が借入額の目安といえます。
とはいえ、自己資金が300万円あったとしても、必ず900万円を借り入れできる訳ではありません。創業融資の対象となるのは、あくまでも新たに事業を始めるにあたって必要な資金です。
例えば、飲食店を開業する場合、厨房設備や内装費などの設備資金、テナント料、材料仕入や人件費などの運転資金が創業融資の対象になります。
融資申込額を考える際は、全体の資金計画から自己資金分の300万円を控除した残額がいくらになるかをチェックしたうえで検討しましょう。
創業融資1,000万円を受けるための自己資金はいくら必要?
創業融資として1,000万円借り入れるには、自己資金額はいくら必要になるでしょうか。
これまでに解説した借入額の目安を基準として考えると、1000万円を借り入れる場合の自己資金額は、その3分の1となる約350万円程度は必要だと考えられます。
とはいえ、創業融資に限らず、融資を受ける場合には、全体の資金計画の中で、自己資金がいくら出せるのかを逆算して考える必要があります。
例えば、全体の資金計画が1,500万円の場合で、自己資金が100万円しか出せないのであれば、それを踏まえて1,400万円の融資を申し込まなくてはなりません。
ただし、融資額が高額になる場合は、その分返済負担も大きくなります。
事業計画を立てる際には、コスト削減の意識を持ち、資金計画と借入返済とのバランスを考えて計画を立てるようにしましょう。
自己資金ゼロでも創業融資は可能?
自己資金がゼロの場合、創業融資を受けることはできるのでしょうか。
結論からいうと、自己資金がゼロでも創業融資を受けられる可能性はあります。
しかし、自己資金ゼロで創業する場合、返済負担も大きくなってしまうため、銀行では審査が通らない可能性が高いです。
銀行が融資の審査をする際には、代表者の信用情報や経験・経歴だけでなく、代表者の人間性もチェックしています。新たに事業を始めるということは、それ相応の覚悟を持っている必要があります。
その覚悟が見えず、開業資金のすべてを融資で賄おうと考えているとなると「考えが甘い」と思われる可能性は否めず、銀行で創業融資を借りるのは難しいでしょう。
銀行は厳しいが、公庫の「新創業融資制度」なら可能性あり
先述のとおり、自己資金ゼロで銀行から創業融資を借りるのは難しいです。しかし、公庫の「新創業融資制度」であれば、自己資金がなくても融資を受けられる可能性があります。
日本政策金融公庫の取り扱っている創業者向けの融資制度には、自己資金に関する要件がありません。
融資審査の可否を決めるうえで、自己資金の有無は判断材料の1つではありますが、要件として定められている訳ではないため、自己資金ゼロでも借りられる可能性があるのです。
日本政策金融公庫を利用して創業融資を受けようと考えている場合、自己資金ゼロでも申し込みができる点は理解しておくと良いでしょう。
とはいえ、融資審査においては、自己資金が多いほど返済負担も抑えられるため、返済能力があると判断しやすくなります。
また、自己資金は開業に向けた決意や覚悟の表れとして評価してもらえる可能性が高くなります。
もしも、現時点で自己資金がない場合には、まずは少しでも自己資金を貯めることから始めてみるのが開業に向けた第一歩といえるでしょう。