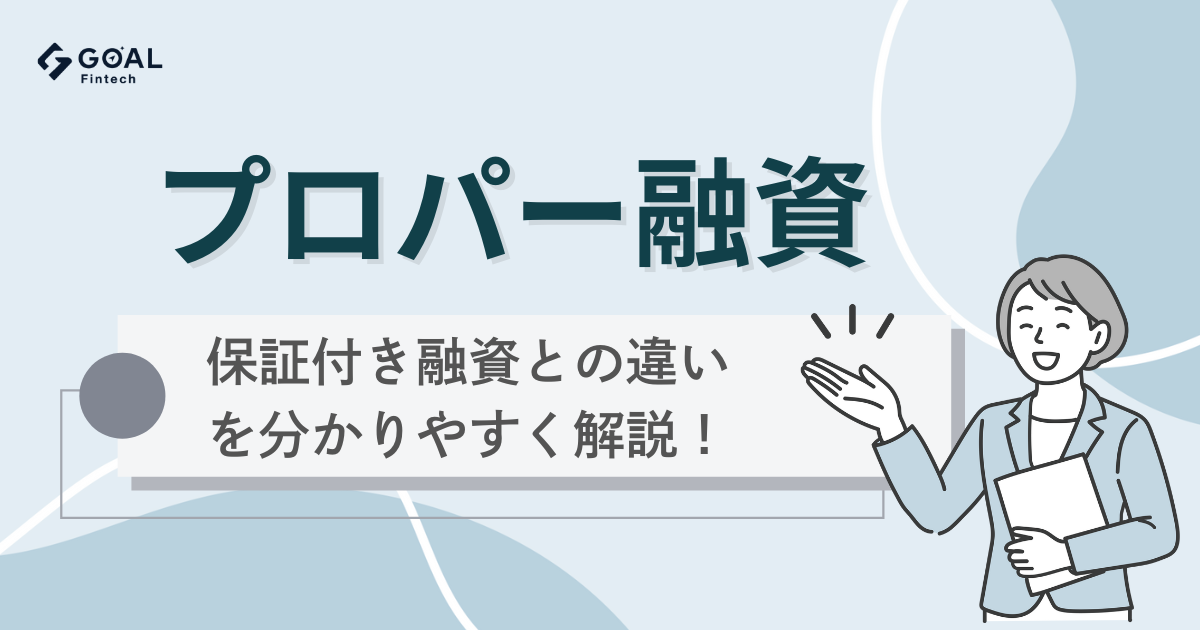事業資金の調達方法の中でも、プロパー融資は非常に重要な調達方法です。
審査基準が厳しいため、利用できるケースは限られますが、金融機関からの信頼を得ることで、将来的に安定した資金調達が可能になります。
今回は、資金調達を検討している中小企業の経営者や個人事業主向けに、プロパー融資の基本知識をわかりやすく解説します。
- 銀行融資の中でも厳格な審査が行われる
- 基本的には保証付融資を利用する
- 低金利で借入できる可能性がある
まずは仕組みを正しく理解し、プロパー融資を目指すための第一歩を踏み出しましょう。
プロパー融資とは?わかりやすく解説
プロパー融資とは、銀行や信用帰庫などの金融機関が、信用保証協会などの保証を付けずに資金を貸し付ける融資のことです。
プロパー融資は、信用保証協会を通さず、銀行が独自の審査基準で貸出を行うため、債務不履行による損失リスクも大きく、誰しもが融資を受けられる訳ではありません。
しかし、借入側には、保証料の負担がなく、柔軟な対応が期待できるなどのメリットを享受できる融資といえます。
では、プロパー融資とは、どのような仕組みで、どのような場合に利用できるのでしょうか。
ここでは、プロパー融資の仕組みやプロパー融資を利用するケースについて詳しく解説します。
プロパー融資の仕組み
プロパー融資は、銀行や信用金庫などの金融機関が保証協会の保証を立てずに直接資金を貸し出す融資ですが、一体どのような仕組みになっているのでしょうか。
ここでは、プロパー融資の仕組みについて、以下のとおり解説します。
- 銀行が保証協会を通さず、直接リスクを取って貸し出す融資
- 保証協会の審査を挟まないため、銀行独自の基準で判断
それぞれ見ていきましょう。
銀行が保証協会を通さず、直接リスクを取って貸し出す融資
プロパー融資は、銀行が保証協会を通さず、直接リスクを取って貸し出す融資です。
信用保証協会の保証が付いている場合、貸出先が返済できない状態になったとしても、保証協会に「代位弁済請求」を行うことで保証協会が債務者に代わって一定割合(80〜100%)を返済してくれます。
そのため、金融機関は貸し倒れ発生による損失リスクを抑えられるのです。
なお、代位弁済を受けた企業は、残った債務を銀行ではなく保証協会に返済していくことになります。銀行としては、貸し倒れによる損失を抑えられるだけでなく、債務の返済を履行させる手間を省くことができ、早期の債権回収が可能です。
一方のプロパー融資は、保証協会の保証がありません。万が一、貸出先が返済できない状態になると、残金のすべてが貸し倒れとなってしまいます。
このように、プロパー融資は、信用保証付きの融資よりもリスクの高い融資といえるのです。
保証協会の審査を挟まないため、銀行独自の基準で判断
プロパー融資は、保証協会の審査を挟まないため、融資審査は銀行独自の基準で行われます。
プロパー融資は、直接損失を被る可能性があるため、必然的に融資審査も厳しくなる傾向が強いといえるでしょう。
一方、信用保証協会保証付き融資は、保証協会が保証を承諾することが前提であり、融資の可否判断は保証協会に委ねられる側面が強いです。
とはいえ、保証協会が保証を承諾したからといって100%融資ができる訳ではありません。保証協会が保証を承諾したとしても、その後の銀行内の審査で融資が承認されないケースも考えられます。
また、業種などによっては信用保証協会を利用できない場合もあり、プロパー融資でしか対応できないケースも考えられるでしょう。こうした場合には、保証協会を通さずにプロパー融資で対応するケースも考えられます。
プロパー融資を利用するケース
プロパー融資は、信用保証協会の保証を付けずに銀行独自の基準で融資を行うものですが、誰でも利用できる融資ではありません。
ここでは、以下のプロパー融資を利用するケースについて解説します。
- 長年の取引実績がある法人・個人事業主
- 財務内容が安定している企業
- 設備投資や大型資金調達をしたい場合
長年の取引実績がある法人・個人事業主
銀行との長年の取引実績がある法人や個人事業主の場合、プロパー融資を利用できるケースとしてあげられます。
過去に保証協会保証付の融資を利用して完済した実績がある場合や、預金なども含めて取引のメイン化が図られている事業者はプロパー融資を利用できる可能性が高いです。
これまでの取引実績に問題がなければ、プロパー融資を実行しても返済を履行できる可能性が高いと判断しやすいでしょう。
また、預金口座に売上金が入金されるなど、預金取引のメイン化が構築できている場合も有利です。
銀行は、事業内容や決算書などの財務情報はもちろんですが、経営者の人柄も重視しています。経営者が信用のおける人物であれば、例え経営状況が厳しくても手を差し伸べてくれる可能性も考えられるでしょう。
銀行から信用を得るうえで、長年の取引実績は何よりの証拠といえます。
このような点から、長年の取引実績がある法人や個人事業主は、銀行との信頼構築が図れているため、プロパー融資を利用するケースが考えられるでしょう。
財務内容が安定している企業
財務内容が安定している企業もプロパー融資を利用するケースが考えられます。
自己資本比率が高く、返済能力が高いと判断できる場合、貸し倒れの発生による損失リスクが低いと考えられるため、銀行もプロパー融資で対応しやすいです。
また、財務内容が安定している場合には、保証協会保証付融資の金利よりも低金利で借り入れできるケースも考えられるでしょう。
プロパー融資を利用したいと考えるのであれば、銀行が融資したいと思えるような財務内容へと見直ししていくことが大切です。既存事業の拡大や新規顧客の獲得、原価見直しなどを実践し、財務内容の安定化に務めましょう。
このように、財務内容が安定している企業は、プロパー融資を利用するケースが考えられます。
設備投資や大型資金調達をしたい場合
設備投資や大型資金を調達したい場合には、プロパー融資を利用するケースが考えられます。
保証協会の融資限度額は、無担保で8,000万円、担保がある場合は2億8,000万円となっており、それ以上の金額の場合は、保証協会の保証は受けられません。
工場建設など、大規模な設備投資が必要な場合には、保証協会の融資だけでは対応しきれないケースも想定されます。こうした場合には、保証協会保証付ではなく、プロパー融資を利用するケースが考えられるでしょう。
また、プロパー融資を利用する場合でも、保証協会保証付の融資を併用した協調融資を利用したり、日本政策金融公庫などの複数の金融機関融資を組み合わせたりするケースもあります。
ほかにも、数十億円単位の融資が必要な場合には、アレンジャーと呼ばれる取りまとめ金融機関を中心に、複数の金融機関が参加して融資を組成するシンジケートローンといった融資もあります。
プロパー融資と保証付融資の違い
銀行がリスクを取って直接資金を貸し付ける「プロパー融資」と、信用保証協会の保証を利用して融資を行う「保証付融資」には具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、プロパー融資と保証付融資の違いについて解説します。
保証付融資(信用保証協会付融資)とは
保証付融資(信用保証協会付融資)とは、信用保証協会法に基づいて設立された公的機関である信用保証協会の保証を利用して資金調達する融資方法です。
信用保証協会が「公的な保証人」となることで、個人事業主や中小企業者の円滑な資金調達の支援が目的であり、47都道府県と4市(横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市)に設置されています。
さまざまな業種が保証対象となっており、中小事業者の多様な資金ニーズに応えることで、地域経済の発展に貢献する重要な役割を担っているといえるでしょう。
ただし、農林漁業、金融業、学校・宗教法人、非営利団体、LLP(有限責任事業組合)風営法第2条第5項に規定される性風俗関連特殊営業などは保証の対象外業種とされています。
なお、農林漁業に関しては、独立行政法人農林漁業信用基金による基金保証制度が利用可能です。
保証付融資の特徴について以下のとおり解説します。
- 保証協会が借入を保証することで、銀行はリスクを軽減
- 個人事業主や創業間もない企業でも利用しやすい
それぞれ見ていきましょう。
保証協会が借入を保証することで、銀行はリスクを軽減
保証付融資は、信用保証協会が「公的な保証人」として銀行の借入を保証することで、銀行のリスクを軽減できる特徴があります。
個人事業主や中小企業などの中小事業者は、事業規模も小さく、大企業や大手企業と比べて信用力に劣る場合が多いです。銀行の融資審査においても、事業内容や財務内容などから融資がしにくいケースが考えられるでしょう。
こうした場合でも、保証協会が債務を保証してくれれば、債務者が返済不履行に陥っても銀行は貸し倒れによる損失リスクを軽減できるので、金融機関も融資しやすくなります。
このように保証協会保証付融資は、地域の事業者の円滑な資金調達を支援するために重要な役割を担っており、銀行のリスク軽減に役立っているのです。
個人事業主や創業間もない企業でも利用しやすい
保証付き融資の特徴として、個人事業主や創業間もない企業でも利用しやすい点があげられます。
個人事業主は、法人と比べて科目内訳明細まで作成していない場合が多く、不透明な部分も多いです。また、創業間もない企業は、返済能力を示す材料に乏しいケースが多く、プロパーでの取り組みは難しいといえるでしょう。
しかし、信用保証協会は、中小事業者の資金調達を支援するために設立された公的制度であり、地域経済の発展に寄与することが目的です。そのため、保証協会の制度融資の中には、個人事業主などの小規模事業者向けの制度や、独立・新規開業などを支援する制度も設けられています。
このように、個人事業主や創業間もない企業でも融資を受けやすくなる点は、保証協会保証付融資の特徴といえます。
プロパー融資と保証付融資の違いを比較
プロパー融資と保証付融資には、どのような違いがあるでしょうか。
プロパー融資と保証付融資の違いについて、以下の表のとおりまとめましたので、見ていきましょう。
| 項目 | プロパー融資 | 保証付融資 |
|---|---|---|
| 審査主体 | 銀行 | 信用保証協会などの保証会社 |
| 保証人 | 金融機関によって異なる※経営者保証ガイドラインの要件を満たしている場合は不要となるケース有 | 原則、法人代表者のみ※経営者保証ガイドラインの要件を満たしている場合は不要となるケース有 |
| 金利 | 年2~3%程度※金融機関によって異なる | 年1~3%程度※保証料除く |
| 限度額 | なし※金融機関によって異なる | 無担保:8,000万円有担保:2億8,000万円 |
プロパー融資は銀行が独自の基準で審査を行いますが、保証付融資は保証協会の保証承諾が前提です。そのため、審査主体は保証協会となる点が異なります。
融資限度額に関しても、プロパー融資の場合は金融機関によって異なりますが、特に限度額は決まっていません。しかし、保証協会は無担保の場合は8,000万円、有担保の場合でも2億8,000万円までと限度額が決まっています。限度額以上の融資は利用できない点は注意が必要です。
また、金利面を比較すると、保証協会よりもプロパー融資の方が高くなりやすい傾向にあります。
大企業や財務内容が安定している優良企業の場合、保証付融資の金利よりも低くなるケースも考えられるでしょう。
しかし、小規模事業者や中小企業の場合でプロパー融資を受けている場合、保証付融資よりもリスクを取って融資を行っているケースがほとんどです。そのため、融資金利が高いケースが多いといえるでしょう。
なお、保証人については、平成26年2月の「経営者保証に関するガイドライン」適用開始以降は、要件を満たしている場合には経営者保証を不要とするケースが増えています。
保証付融資においても、ガイドラインを満たしている場合には不要とするケースや、経営者保証なしで取り組むための融資制度も制定されています。
プロパー融資と保証付融資では上記のような違いがある点は理解しておきましょう。
プロパー融資に関するよくある質問
ここでは、銀行融資におけるプロパー融資に関するよくある質問についてご紹介します。
- 審査時に信用情報は確認されますか?
一般的に、プロパー融資では経営者の個人信用情報は確認しないケースが多いです。
プロパー融資は、銀行や信用金庫などの金融機関が企業の財務状況、事業計画などを独自の基準で審査しています。審査の際には、経営者自身の個人信用情報よりも企業自体の返済能力の有無や事業の将来性を重視する傾向が強いです。
そのため、個人信用情報は確認されないケースが多いといえるでしょう。
ただし、プロパー融資は、銀行にとって損失が発生するリスクが高いです。企業の財務状況が悪かったり、これまでの取引実績が少なかったりする場合には、個人信用情報を確認されるケースも考えられるでしょう。
- 金利はどのくらいですか?
プロパー融資の金利は一律ではありませんが、年1~3%程度が一般的な相場です。
プロパー融資の金利は、企業の信用力や事業規模、決算内容、業種、借入期間、保証人や担保の有無によって個別に決定されます。経営状態がよく、返済能力が高いと判断できる企業は低利で借りられる可能性が高いです。
一方、不安定業種や事業規模がそれほど大きくない場合や、保全状況が悪い、保証人なしなどの借入条件によっても異なる金利設定になるケースが多いでしょう。
例えば、養殖業や畜産業などは、信用保証協会が利用できない業種のため、融資を行うにはプロパー融資で対応せざるを得ないケースが想定されます。
しかし、養殖業や畜産業は、稚魚や子牛・子豚などを仕入れてから販売までの期間が長期間に及ぶだけでなく、病気や災害による死亡リスクも高い業種です。そのため、通常の相場金利よりも高くなる傾向が強いといえます。
プロパー融資は、融資する企業の状況によって金利が大きく変わる点は注意しておきましょう。
- プロパー融資を受けるにはどうしたらいいですか?
プロパー融資を受けるには、企業の信用力を高める必要があります。
まずは信用保証付き融資を受け、毎月の約定返済を履行するなどの返済実績を積んでいきましょう。また、プロパー融資は、銀行がリスクを取って行う融資のため、銀行が融資したいと思えるような決算内容にすることも重要です。
更には、プロパー融資を受けたい銀行の口座を売上入金口座として指定したり、給与振込契約や口座振替などの機能取引を増やしたりといった預金取引のメイン化を図っておくことも有利に働きます。
日頃から金融機関の担当者とコミュニケーションを取り、相談しやすい関係を構築しておくと良いでしょう。