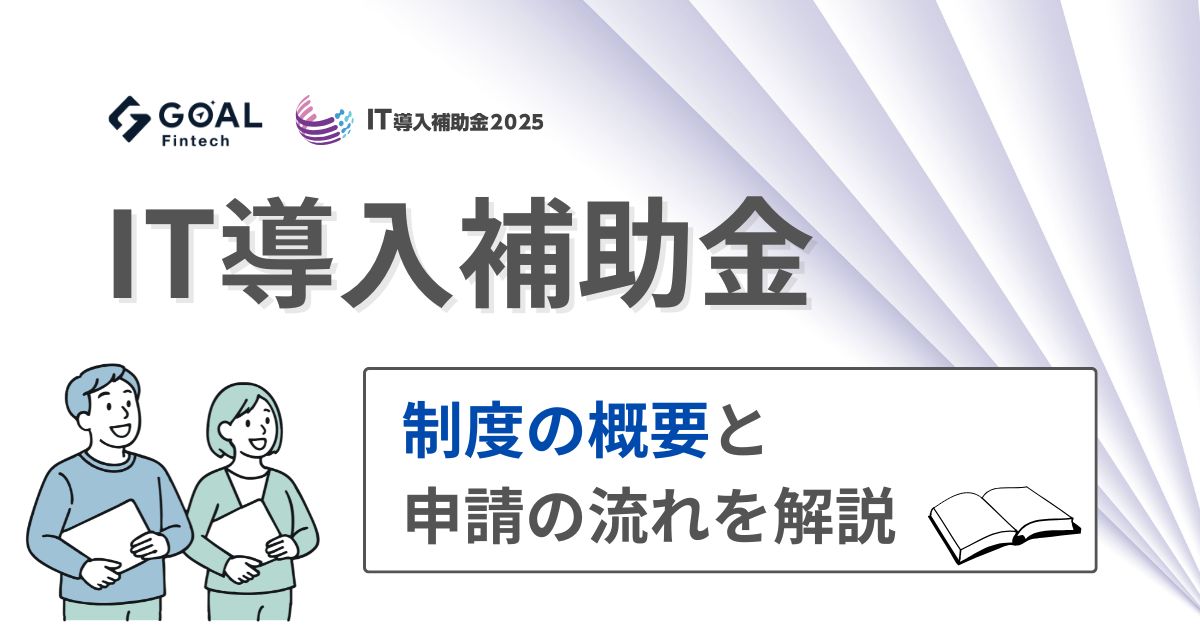補助金制度の中でも特に人気が高いのが「IT導入補助金」です。毎年、国の予算が組まれ、継続的に実施されている制度です。
2025年度も「IT導入補助金2025」として受付がスタートしています。
補助金制度は事業者が日常的に利用するものではありません。
「IT導入補助金って何に使えるの?」
「他の補助金より通りやすいって本当?」
といった疑問や、制度の詳細まで理解できていない方も多いのではないでしょうか。
たしかに、IT導入補助金は比較的活用しやすい制度です。しかし、その原資は税金であり、申請内容や使い道には厳格なルールがあります。適切に活用しなければ「不正受給」とみなされる恐れもあります。
そこで今回は、IT導入補助金2025を検討している方に向けて、申請条件や活用のポイントをわかりやすく解説していきます。
制度を正しく理解し、有効活用するための参考にしてください。
IT導入補助金とは?
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際の費用を国が一部補助する制度です。
業務効率化や生産性向上、またインボイス制度への対応などを目的としています。ソフトウェア、クラウドサービス、業務支援ツールなどが補助対象となります。
申請には、事前に登録された「IT導入支援事業者」を通じて手続きを行う必要があり、単独での申請はできません。
また、補助額や補助率は導入するツールの内容や事業規模により異なります。毎年制度の内容や条件も更新されるため注意が必要です。
2025年度も予算が確保されており、例年同様に通常枠やインボイス対応枠など複数の類型が用意されています。
IT導入補助金を活用することで、初期費用の負担を軽減しながら、業務のDX(デジタル化)を進めることができます。
他の補助金制度と比較して、「交付決定事業者の多さ」や「様々な事業者が活用できる」点が特徴的です。
交付決定事業者が多い
一般的な補助金制度はあまり知られておらず、対象となる事業者であっても申請されていないケースが少なくありません。
しかし、IT導入補助金は名称もキャッチーで知名度が高く、実際の申請数・交付決定数も多いのが特徴です。
たとえば、2025年6月18日に締め切られた第1次公募の実績は下記のとおりです。
| 区分 | 申請件数 | 交付決定数 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 2,979 | 1,511 |
| インボイス枠(対応類型) | 6,446 | 3,710 |
申請件数・採択件数ともに高い水準であり、他の補助金と比べて活用のハードルが低いことがわかります。
地方自治体の補助金などは予算の都合ですぐに募集が締め切られてしまうこともありますが、IT導入補助金は複数の締切日が設けられており、継続的に申請・交付が行われているのが大きな特徴です。
様々な事業者が活用できる
IT導入補助金は、業種や業態を問わず、幅広い事業者に利用されているのが特徴です。
現在では、業務のデジタル化・効率化があらゆる業種に求められています。製造業、建設業、小売業、医療・福祉業など、いわゆる「レガシー産業」でもITツール導入が進んでいます。
たとえば、勤怠管理システムや販売管理ソフト、会計ソフト、受発注管理システムなどは、業種を問わず導入のニーズが高いといえます。
こうしたツールを導入する際にIT導入補助金を活用することで、コストを抑えながら業務改善を図ることができます。
IT導入補助金の対象者と対象条件
補助金制度は要件が複雑でわかりづらく「自分の会社が対象かどうか分からない」「手続きが大変そう」といった理由で、申請をあきらめてしまうケースも少なくありません。
まずは簡単に、IT導入補助金の対象者と対象条件について見ていきましょう。
申請対象となる事業者
IT導入補助金は、主に中小企業や小規模事業者を対象としており、基本的に大企業は対象外です。
目的は、ITツールの導入にハードルを感じる中小規模の事業者を支援することにあります。
対象となるのは法人だけでなく、個人事業主の方も含まれます。たとえば、飲食店経営者やIT系フリーランスの方などにも活用実績があります。
要件は業種によって異なり、たとえば建設業の場合は「資本金3億円以下または従業員300人以下」が対象です。
ほかにも複雑な条件があるため、不安な場合は専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
また、IT導入補助金2025の公式サイトでは、「申請対象者チェッカー」が用意されています。組織形態と業種を選ぶだけで自社が対象かどうかを簡単に確認できるのでチェックしておきましょう。
対象となる経費・ITツールの例
IT導入補助金は、どんなITツールにも使えるわけではなく、「IT導入支援事業者」として事務局に登録されたツールのみが対象となります。
そのため、いくら自社にとって良さそうなツールであっても、登録されていない場合は補助金の対象外となるので注意が必要です。
利用を検討しているツールが対象かどうかは、IT導入補助金の公式サイトにある「ITツール・IT導入支援事業者検索」で事前に確認しておきましょう。
対象となる経費の例としては、ソフトウェア・クラウドサービス・ハードウェアなどがあります。
なお、パソコンなどのハードウェアも補助対象になることはありますが、類型や条件によって制限があるため、必ず事前に確認しておきましょう。
IT導入補助金2025の申請方法を解説
IT導入補助金は、ITベンダー(IT導入支援事業者)と一緒に進めていく制度ですが、事業者自身も申請の流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、IT導入補助金2025の申請方法について、「事前準備」と「申請の流れ」の2つのステップに分けて詳しく解説していきます。
特に、事前準備は時間がかかる項目もあるため、早めに対応しておきましょう。
申請に必要な準備
IT導入補助金の申請には、下記の4つの準備が必要です。
- gBizIDの取得
- セキュリティアクション宣言
- 事業計画書の作成
- 導入予定のITベンダー(IT導入支援事業者)との相談
gBizIDの取得とセキュリティアクション宣言は比較的すぐに完了できるため、導入を決めている場合は早めに済ませておきましょう。
一方で、事業計画書の作成やITベンダーとの相談は時間がかかることが多いため、早い段階で着手することをおすすめします。
gBizIDの取得
まず、IT導入補助金を申請の検討をしている方は、早めにgBizID(ジービズアイディー)の取得をしておきましょう。
gBizIDとは、経済産業省が提供するオンライン申請共通アカウントです。補助金の電子申請を行う際に使用します。
必要なのは「gBizIDプライム」という最上位アカウントであり、取得には印鑑証明書と申請書の郵送提出が必要です。
原則として登録の代行ができず事業者本人が手続きをしなければなりません。また、申請から発行までは1〜2週間程度かかるため、早めの準備がポイントです。
gBizIDは、一度取得しておけばIT導入補助金以外の国の補助金申請でも使用できます。
セキュリティアクション宣言
gBizIDの取得に加えて「セキュリティアクション」の宣言も必要です。
セキュリティアクションとは、独立行政法人IPA(情報処理推進機構)が推進する、中小企業の情報セキュリティ対策を促進する制度です。
申請に必要なのは「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかの宣言です。多くの場合は★一つ星で要件を満たします。
宣言の手続きは無料で行うことができ、所要時間は10〜15分程度。
専用サイトから必要事項を入力・申請すると、宣言済みロゴを取得できます。
ITツールの導入はセキュリティリスクにも直結するため、情報セキュリティの取り組みを事前に表明することが補助金申請の要件となっています。
まだ宣言していない場合は、gBizIDの取得と並行して進めておきましょう。
事業計画書の作成
IT導入補助金の申請には、事業計画書の作成が必須です。
とはいえ、具体的な書き方はIT導入支援事業者(ITベンダー)と相談しながら進めることができるため、専門的な知識がなくても心配は不要です。
ただし、スムーズに計画書を作成するためには、事前に下記の点を整理しておくのがよいでしょう。
- ITツールを導入したい目的
- 導入後に、どんな効果(業務効率化・コスト削減など)が期待できるのか
- ツール導入によって、事業全体にどのような利益をもたらすか
自社の現状を棚卸しておくと、情報を整理しやすくなります。
また、補助金の交付後には実績報告の提出も必要になるため、事業計画書はできるだけ具体的かつ丁寧に作成しておくと、その後の手続きにも役立ちます。
導入予定のITベンダー(IT導入支援事業者)との相談
特定の気になるITツールがある場合は、提供元や提携しているIT導入支援事業者に相談しましょう。
多くのツールでは、公式サイトに「IT導入補助金対応」などの記載があり、補助金に関する相談窓口が用意されています。
問い合わせれば、申請の流れや必要な準備について案内してくれます。
また、IT導入補助金2025の公式サイトには「IT導入支援事業者検索ツール」が用意されています。
たとえば、「freee」などのキーワードで検索すれば、そのツールの導入支援を行っている支援事業者の一覧が表示されます。その中から、支援事業者を選んで相談を進めましょう。
なお、弊社でも最適なITツールや支援事業者のご紹介が可能です。ツール選定でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
申請の流れ
IT導入補助金の申請は、以下の5つのステップに分かれています。
各ステップの細かい内容をすべて覚える必要はありませんが、全体の流れを把握しておくことが大切です。
- ITベンダーとスケジュールと事業計画の策定
- 申請フォームから電子申請(ITベンダーが代理申請)
- 採択通知の受領
- ツールの導入・支払い・実績報告
- 補助金交付
特に重要なのは、ITツールの費用は先払いになるという点です。補助金は後から支払われるため、資金繰りには十分注意して計画を立てましょう。
ITベンダーとスケジュールと事業計画の策定
導入予定のITツールとITベンダー(IT導入支援事業者)が決まったら、補助金の申請に向けて、スケジュールや事業計画の策定を進めていきましょう。
ITベンダーは、複数の事業者への導入支援を行っており、申請から導入・実績報告までの流れを熟知しています。そのため、スケジュール調整や書類作成もスムーズに進められます。申請者側の負担は大きくないので安心です。
事業計画の中では、導入するITツールによってどのような効果が見込まれるのか、導入後の運用方法や事業への影響について事務局へ伝わるようにまとめる必要があります。
また、IT導入補助金の細かい制度内容や不明点がある場合も、ITベンダーに相談すれば具体的なアドバイスが得られるので、不安な点は早めに確認しておくのがよいでしょう。
申請フォームから電子申請(ITベンダーが代理申請)
IT導入補助金の申請は、ITベンダー(IT導入支援事業者)と申請者が共同で行う形になっています。
電子申請は、ITベンダーが代理で行いますが、申請者側でも一部作業が必要となるため、事前に人員やスケジュールを確保しておきましょう。
基本的には、ITベンダーの指示や申請スケジュールに沿って手続きを進めていくことになります。
過去の申請実績があるベンダーであれば、全体の流れをスムーズに誘導してくれるので安心です。
ただし、申請には多くの書類が必要であり、内容に不備があると事務局から確認や差し戻しが入ることもあります。
その場合、審査や交付決定までに時間がかかってしまうこともあるため、書類は丁寧に準備し、正確に提出しましょう。
採択通知の受領
申請内容に問題がなければ、事務局から採択通知が届きます。この通知をもって、正式に補助金の対象として認められたことになります。
注意すべき点として、IT導入補助金は「事前着手禁止型」の制度です。
つまり、採択通知が届く前にツールの導入や費用の支払いを行った場合、その経費は補助金の対象外となってしまいます。
補助金を確実に受け取るためには、必ず採択通知を受領してから契約・導入・支払いを行うようにしましょう。
このタイミングを誤ると、補助金を受けられなくなるため十分注意しましょう。
ツールの導入・支払い・実績報告
採択通知を受け取った後は、正式にツールの導入や支払い手続きを進めます。
この際に領収書や契約書、請求書などの証憑書類は、実績報告で提出が求められるため、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
IT導入補助金は後払い方式のため、申請者が一度全額を支払う必要があります。
ツールによっては、数十万円〜百万円を超える出費になることもあるため、キャッシュフローには十分な注意が必要です。
万が一、補助金が交付されなかった場合でも、事業に支障が出ないように、導入前に財務状況をしっかりと確認しておくことが重要です。
補助金ありきの資金計画ではなく、現実的な予算管理を行いましょう。
補助金交付
一連の申請・実績報告に問題がなければ、指定の口座に補助金が振り込まれます。
ただし、交付された後も終わりではありません。効果報告として、導入したITツールの活用状況や効果に関する報告が求められます。
この報告を怠ると、補助金の返還を求められるケースもあるため要注意です。補助金を受け取った後も最後まで責任を持って対応する必要があります。
IT導入補助金は、ITベンダーのサポートを受けられるとはいえ、申請者側にも一定の手続きや制度理解が求められます。
スムーズな対応のためにも、社内で担当者を明確に決めておくことをおすすめします。
IT導入補助金に関するよくある質問と注意点
IT導入補助金に関するよくある質問と注意点について見ていきましょう。
- 採択率はどのくらいですか?
IT導入補助金の採択率は比較的高く、2025年の第1次締め切りにおいては5割を超えています。
多くの場合において、申請は専門家のサポートを受けながら行うため、要件を満たした状態で提出されることが多く、採択率も高くなる傾向にあります。
- 申請してからどのくらいの期間で補助金が振り込まれますか?
申請のタイミングにもよりますが、申請から補助金が振り込まれるまでには、一般的に3〜6か月程度かかります。
特に、ツールの費用を支払ってから、補助金が振り込まれるまではタイムラグがあるのでキャッシュフローに注意しましょう。
- 自分で申請できますか?
申請はIT導入支援事業者との共同申請となります。そのため、申請者単独での申請はできません。
対象ツールを取り扱っているITベンダーを通して進めていきましょう。